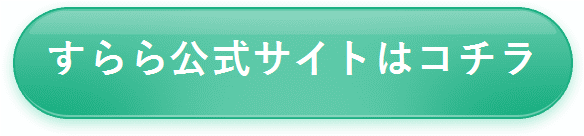すららは不登校でも出席扱いになる?なぜ?出席扱いになる理由について
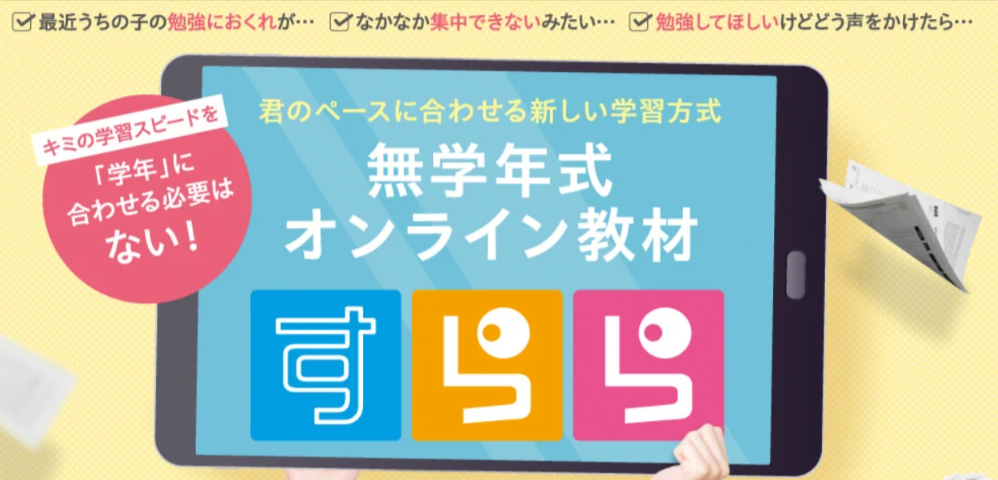
不登校のお子さんをもつご家庭にとって、「家庭学習でも学校の出席扱いになるのか?」はとても大きな関心事だと思います。
実は、文部科学省のガイドラインでは、一定の条件を満たせば自宅学習を出席扱いにできるとされています。
そして「すらら」は、その条件を満たす教材のひとつとして、多くの不登校の子どもたちに選ばれています。
ここでは、なぜすららが出席扱いとして認められやすいのか、その具体的な理由を5つの視点から解説していきます。
学校との関係を保ちながら、お子さんの自信や学びを支えていける教材かどうかを見極めるための参考になればうれしいです。
理由1・学習の質と記録の証明がしっかりしている
すららが「出席扱い」として認められる理由の一つに、学習の質とその証明のしやすさがあります。
すららでは、学習した時間、正答率、取り組んだ単元などの情報がシステム上に自動的に記録され、レポートとして出力できる仕組みがあります。
これにより、保護者が一つ一つ記録を取る必要がなく、学校側に対しても「客観的な学習証拠」として提示できるのです。
これらの記録は、学校側が「きちんとした学習が行われている」と判断する上で、非常に有効な材料となります。
出席扱いが認められるかどうかは、こうした“信頼できるエビデンス”があるかどうかで決まるとも言えるでしょう。
学校側に「客観的な学習記録レポート」を提出できる
すららの学習システムは、進捗や成果をグラフや数値で「見える化」してくれるため、保護者が学校に提出する際にとても便利です。
誰が見ても一目で分かるレポート形式なので、担任や校長先生にも納得してもらいやすいのがポイントです。
特に「どうやって学校に説明すればいいか分からない」という保護者の方にとって、大きな安心材料になるでしょう。
保護者の手間なく、自動的に学習状況が可視化される/これが学校側からも「安心材料」として評価されやすい
毎日の学習状況が自動で記録されるすららは、保護者の負担を大きく軽減してくれます。
学習時間や内容をいちいちメモしなくても、すべての履歴が蓄積され、必要なときにレポート化できます。
学校側としても、こうした自動記録の存在は「正確な学習管理ができている」という安心材料になり、出席扱いを判断する際にプラスに働きやすいのです。
理由2・個別最適な学習計画と継続支援がある
すららは、単なる教材提供にとどまらず、学習を支える「人の支援」も強みのひとつです。
学習の進め方や量は子どもによって異なりますが、すららでは専任の「すららコーチ」がついて学習計画を立て、進捗を確認しながらアドバイスをくれます。
この「継続的な支援」が、学校側からも高く評価されている理由の一つです。
また、無学年式のカリキュラムを採用しているため、前の学年に戻ったり、得意な教科を先に進めたりと、柔軟な学習が可能です。
こうした一人ひとりに寄り添った仕組みが、出席扱いとしての信用にもつながっています。
すららはコーチがいることで、学習の「計画性」と「継続性」をセットでアピールできる
学習が出席扱いになるためには、ただ勉強しているだけでなく、「計画性」と「継続性」があるかどうかが重要です。
すららのコーチは、お子さんに合った学習スケジュールを提案し、親御さんにも共有してくれます。
これにより、「なぜこの学習内容なのか」「いつまでにどこまで進むか」といった説明が明確にできるので、学校からも納得されやすくなります。
すららは、専任コーチが継続的にサポートし、学習計画を作成してくれる
家庭で学習を継続することは、簡単なようで実はとても難しいものです。
すららのコーチは、子どものモチベーション維持にも寄り添ってくれる存在です。
定期的にフィードバックをくれることで、学習のリズムが崩れにくくなり、「毎日コツコツやっている」という実績が積み重なります。
これは出席扱い申請の際にも、非常に大きな武器になります。
すららは、無学年式で学習の遅れや進み具合に柔軟に対応してくれる
不登校の子どもには、「前の学年の内容を忘れてしまった」「今さら授業についていけない」というケースもよくあります。
すららなら、学年をまたいで学べるので、苦手を徹底的にやり直すことも、得意な教科を先取りすることも可能です。
子どもの学び直しにも柔軟に対応できるからこそ、無理なく継続でき、結果的に出席扱いの条件を満たすことにつながります。
理由3・家庭・学校・すらら三者で連携ができる
すららの出席扱いが認められやすいもう一つの理由は、「家庭・学校・教材提供者」の三者で連携が取れるように工夫されている点です。
教材を使っているだけでは、なかなか学校とスムーズにやり取りするのは難しいもの。
すららでは、学習記録の提出用フォーマットや、申請書類の準備方法までサポートしてくれる体制が整っています。
担任の先生や校長先生とのやり取りも丁寧にフォローしてくれるので、保護者の負担も大きく減ります。
連携のしやすさは、学校との信頼構築にもつながり、「この子はしっかり学んでいる」と感じてもらえる大きな要因となります。
すららは、必要書類の準備方法の案内をしてくれる
「出席扱いの申請なんて初めてで、何をどうすればいいのか分からない…」そんなときでも安心なのがすららのサポート体制です。
どんな書類が必要か、どう記入すればいいかなど、コーチや運営から丁寧に案内してもらえるため、迷うことなく進められます。
「一人で悩まなくていい」というのが、すららを選ぶ大きなメリットのひとつです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度の申請方法の流れ紹介
不登校の子どもが家庭学習をしている場合、その学習が「出席扱い」になる制度があるのをご存じでしょうか?文部科学省の通知により、一定の条件を満たせば自宅での学習も学校の出席とみなすことができるようになっています。
すららはこの制度に対応した教材の一つであり、実際に多くのご家庭がこの仕組みを活用して、子どもの学びを支えています。
ここでは、すららを利用して出席扱いを申請する方法を4つのステップに分けて解説します。
初めての方でもわかりやすいように、必要書類や注意点も併せて紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
申請方法1・担任・学校に相談する
まず最初に行うべきは、担任や学校との相談です。
どれだけ家庭で学習を頑張っていても、学校側が出席扱いを認めなければ制度は適用されません。
出席扱いは校長の判断で決まるため、早めに学校側と話し合い、制度の利用意思を伝えることが大切です。
その際には、「すららを使って学習している」「定期的に進捗を確認している」といったことを丁寧に説明するようにしましょう。
学校によって手続きの流れが異なる場合もあるため、必要書類や申請タイミングについてもここで確認しておくのがスムーズです。
出席扱いの申請に必要な書類・条件を確認する
学校に相談すると、「この書類を揃えてください」とリストを渡されることがあります。
主に求められるのは学習記録、学習内容の概要、場合によっては医師の意見書などです。
また、「週に何日以上学習しているか」「どの教科をどのくらい取り組んでいるか」など、出席扱いの条件を明確に聞いておきましょう。
すららの学習レポートは、これらの証明に役立つ重要な資料になります。
申請方法2・医師の診断書・意見書を用意(必要な場合のみ)する
不登校の理由が心身の健康状態による場合、医師の診断書が必要になるケースがあります。
特に「心理的理由」「適応障害」「発達障害」などが原因で学校に通えない場合は、医師の意見が出席扱いの判断材料になります。
すべての家庭に必要なわけではありませんが、学校側から提出を求められた場合には準備が必要です。
早めに受診し、学習継続の意義を明確に書いてもらうことが大切です。
不登校の理由によっては、診断書が求められるケースもある
診断書の提出は、特に「医療的ケア」「心理的サポート」が求められる不登校ケースで多く見られます。
これは学校が「医学的な正当性があるかどうか」を確認したい意図があるからです。
診断書には、通学困難の理由だけでなく、「家庭学習を推奨する」といったコメントがあると出席扱いがスムーズになる場合があります。
精神科・心療内科・小児科で「不登校の状態」と「学習継続が望ましい旨」を書いてもらう
診断書は、子どもの状態を正確に伝えるものであると同時に、学習継続の必要性を学校に伝えるツールでもあります。
医師には、すららなどの教材で家庭学習をしている旨を説明し、「学びを止めない選択肢として適している」ことも伝えてもらうと、学校側も前向きに受け止めてくれることが多いです。
申請方法3・すららの学習記録を学校に提出する
出席扱いの申請においてもっとも重要なのが「学習の実績を証明する資料」です。
すららには、子どもがどの単元をどのくらいの時間学習し、どんな成績だったかがわかる「学習進捗レポート」があります。
これをPDFなどで出力し、担任や校長先生に提出します。
また、出席扱い申請書自体は学校側が作成しますが、保護者が記入すべき項目もあるため、連携しながら書類を完成させていきましょう。
学習進捗レポートをダウンロードし担任または校長先生に提出
すららのマイページから、子どもが学習した履歴をレポート形式で出力できます。
日時や内容、正解率などが記録されているため、学習の“証拠”として非常に信頼性が高く、学校側にとっても確認しやすいのが特徴です。
これを月単位などで提出することで、定期的な確認・承認を得やすくなります。
出席扱い申請書を学校で作成(保護者がサポート)
出席扱い申請書は基本的に学校が用意してくれますが、家庭学習の状況や教材内容について保護者が記入する欄が設けられていることが多いです。
すららの特徴やコーチのサポート内容、教材の構成などを具体的に書くと、校長先生の判断がしやすくなります。
わからない場合は、すららコーチに相談するとスムーズです。
申請方法4・学校・教育委員会の承認
必要書類をすべて整え、担任との相談も済んだら、最後に学校長(校長先生)の承認が得られるかどうかがポイントです。
出席扱いは学校長の裁量で判断されるため、事前の信頼関係がとても重要です。
学校によっては、さらに教育委員会への報告や承認が必要になる場合もあります。
すららのような実績のある教材を使用していると、話がスムーズに通りやすくなる傾向があります。
学校長の承認で「出席扱い」が決まる
校長先生が、提出された学習記録や家庭の状況を見て「学校に準ずる学習が行われている」と判断すれば、出席扱いが認められます。
この際、学習の継続性や教材の信頼性が大きな判断材料になりますので、すららのようなサポート体制が整っている教材は非常に有利です。
教育委員会に申請が必要な場合は、学校側と連携して行う
一部の自治体では、出席扱いを教育委員会に申請する必要がある場合もあります。
その場合、保護者が直接やり取りをすることはほとんどなく、学校側が中心となって進めてくれます。
すららのサポートチームも、こうした自治体ごとの対応に慣れているので、困ったときは遠慮せず相談しましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうメリットについて解説
不登校になったとしても、すららのような家庭用ICT教材を活用して「出席扱い」を認めてもらえることで、多くのメリットが得られます。
ただの“欠席”として記録されるのではなく、きちんと学習を継続していることを証明することで、子ども本人の将来や心の安定、そして親御さんの安心感にも大きくつながります。
ここでは、出席扱い制度を利用することで得られる代表的な3つのメリットを具体的にご紹介していきます。
手続きが少し面倒に感じられるかもしれませんが、それに見合った価値は十分にあります。
メリット1・内申点が下がりにくくなる
出席扱いが認められる最大のメリットのひとつは、「出席日数として記録される」ことです。
学校では定期テストの点数だけでなく、授業への出席状況や提出物などが内申点の評価に影響します。
不登校が長引くと、どれだけ能力があっても“出席日数ゼロ”というだけで内申点が下がってしまうこともあります。
しかし、すららを使って出席扱いを得ることで、そのような理不尽な評価を避けられます。
特に中学・高校進学を考える際には、この点が大きな差になるため、学習継続の証明はとても重要です。
出席日数が稼げることで、内申点の評価も悪化しにくい
学校によっては、内申点のなかに“授業態度・出席率”を含めるところが多く、出席日数が少ないだけで評価が低くなるケースも少なくありません。
すららで「学びの継続」が証明できれば、実際に登校していなくても“評価対象”として認めてもらえることがあり、学力だけでなく出席面でも公平な評価が受けられるのです。
中学・高校進学の選択肢が広がる
内申点がある程度キープできていれば、公立高校の推薦入試や、私立高校での出願要件をクリアしやすくなります。
「不登校だったから選択肢が限られてしまった」と感じることなく、自分の希望や実力に合った進学先を選ぶことができるのは、出席扱い制度ならではの恩恵です。
メリット2・「遅れている」「取り戻せない」という不安が減る
不登校になると、「もう授業についていけない」「進級できないかも」といった不安にとらわれる子どもも多いです。
しかし、すららの無学年式の教材なら、自分のペースでじっくりと苦手を克服しながら学ぶことができます。
「今は学校に行けなくても、ちゃんと学んでいる」という実感が持てることで、焦りやプレッシャーから解放され、安心して学習を続けることができます。
遅れを気にせず、「今の自分に合ったペース」で進められる環境は、子どもにとってとても大切な要素です。
すららで継続的に学習することで、授業の遅れを気にしなくていい
学校に行っていない間でも、すららで毎日コツコツ学ぶことで、学習のリズムを崩さずにいられます。
内容も学校の指導要領に沿っているため、再登校したときにもスムーズに授業に戻れるケースが多く、子ども自身の不安も和らぎます。
学習環境が整うことで子どもの自己肯定感が低下しにくい
「できた」「分かった」という小さな成功体験の積み重ねは、子どもにとって大きな自信につながります。
家庭でも学びが続けられることで、「自分はダメなんじゃないか」という思い込みから抜け出し、自己肯定感を保つことができます。
メリット3・親の心の負担が減る
不登校の子どもを抱える親は、精神的にも体力的にも大きな負担を抱えています。
「学校に行かせなきゃ」「勉強はどうするの?」という焦りや罪悪感を一人で抱えてしまうことも。
そんな中、すららを使って出席扱いが認められることで、「ちゃんと学んでいる」「将来に繋がっている」という安心感が生まれます。
また、すららコーチという第三者が関わることで、親子だけで解決しようとするプレッシャーも軽減されます。
サポート体制が整っているからこそ、親も“自分を責めなくていい”環境がつくれるのです。
学校・家庭・すららコーチで協力体制ができる/1人で不安を抱える必要がない
すららを活用すれば、家庭内だけで抱え込む必要はなくなります。
担任の先生や学校との連携、そしてすららコーチのサポートがあることで、学習や進路に関する相談も一人で悩まずに済みます。
親の孤独感が軽減され、結果的に家族全体が少しずつ前向きになれるのです。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための重要な注意点について解説
すららを使った家庭学習で出席扱いを認めてもらうには、ただ学習を継続するだけでは不十分な場合があります。
出席扱いに関する判断は、各学校や自治体の方針に左右されることが多く、特に初めて申請する場合は「どのように伝えるか」「何を準備するか」が重要なポイントになります。
ここでは、出席扱い制度の申請時に気をつけたい具体的な注意点を3つにまとめてご紹介します。
申請をスムーズに通すための心構えとして、ぜひ参考にしてみてください。
注意点1・学校側の理解と協力が必須
出席扱いを受けるには、何よりもまず「学校側が納得してくれるかどうか」が鍵を握っています。
担任や校長先生が「家庭での学習がきちんと行われている」と判断できるだけの根拠を提示する必要があります。
すららは、文部科学省が定める出席扱い制度のガイドラインを満たす内容を備えた教材ですが、それを知らない学校関係者も少なくありません。
まずは教材の内容や実績、学習記録の提出方法などを丁寧に説明し、納得してもらうことが大切です。
「すららは文科省ガイドラインに基づく教材」ということを丁寧に説明する必要がある
学校側がすららの名前を知らない場合も多いため、「文部科学省の定める出席扱い制度の条件を満たしている教材です」と伝えることが重要です。
感覚的に話すより、具体的な制度の名称や、文科省の通知をプリントアウトして一緒に持参すると、信頼感が高まります。
必要に応じて、すららの資料を一緒に持参する/担任だけではなく教頭や校長にも早めに相談する
申請の判断権は基本的に「校長先生」にあります。
担任の先生だけで判断できない場合もあるため、早めに校長・教頭レベルに話を通すことをおすすめします。
また、すららの公式パンフレットやWebサイトの出席扱い説明ページを印刷して持参すると、よりスムーズに話が進みやすくなります。
注意点2・医師の診断書や意見書が必要な場合がある
不登校の原因が「体調不良」「精神的不安」「発達特性」などである場合、出席扱い申請にあたって医師の診断書や意見書が必要となるケースがあります。
特に「なぜ通えないのか」を第三者(=医師)が客観的に説明することで、学校側が安心して出席扱いを認めやすくなるためです。
通院している小児科や心療内科、精神科の先生に、出席扱い申請のための診断書が必要な旨を丁寧に伝え、協力を仰ぎましょう。
不登校の原因が「体調不良」や「精神的な理由」の場合は医師の診断書・意見書が必要になることが多い
たとえ一時的な不調であっても、「家庭学習による出席扱い」に学校が慎重になるケースはあります。
医師による「家庭での学習継続が望ましい」という記載があるだけで、判断が大きく変わることもありますので、相談してみる価値は十分あります。
通っている小児科や心療内科で「出席扱いのための診断書が欲しい」と伝える
診断書を依頼する際は、「不登校の状態」と「家庭学習の必要性」の2点を含めて記載してほしいことを明確に伝えると良いです。
特に小児科医や心療内科医はこのような申請に慣れていない場合もあるので、保護者がしっかり意図を伝えることが大切です。
医師に「家庭学習の状況」や「意欲」を具体的に説明して、前向きな記載をお願いする
医師は、家庭での様子が見えないため、記載に迷うこともあります。
事前に「子どもは毎日〇時間、すららで学習しています」「コーチのサポートも受けて計画的に進めています」など、具体的な情報を伝えることで、より正確で前向きな診断内容につながります。
注意点3・ 学習時間・内容が「学校に準ずる水準」であること
出席扱いとして認められるには、家庭学習が「自習」ではなく「学校の教育活動に準じている」必要があります。
これは、すららのような学習指導要領に準拠した教材を使っていれば問題ありませんが、「とりあえず市販のドリルをやらせている」だけでは出席扱いにはなりません。
また、学習時間もあまりに短いと「十分な学習が行われていない」と判断される可能性があるため、週単位・月単位での記録を残しておくと安心です。
出席扱いにするためには、「単なる自習」ではNG/「学校の授業に準じた学習内容」である必要がある
たとえば国語・算数・理科・社会といった教科がバランスよくカバーされていて、学年に応じたカリキュラムに沿っていることが求められます。
すららはこの点をクリアしている教材ですが、申請時にはその根拠も一緒に伝えると説得力が増します。
学習時間は、学校の授業時間に近い形を意識(目安:1日2〜3時間程度)する
出席扱いとして認められるためには、学習内容の質だけでなく「学習量」も大きなポイントになります。
家庭学習だからといって1日30分程度の学習では、学校と同等の教育効果があるとは言えず、出席扱いとして認められにくくなってしまう可能性があります。
そのため、すららを使った学習では、1日あたり2〜3時間程度を目安に、コンスタントに学習を進めていくことが大切です。
すららは短時間学習にも対応していますが、積み重ねることで総時間が確保でき、学校側からも納得されやすくなります。
全教科をバランスよく進める(主要教科だけだとNGな場合もある)
すららでは、国語・算数(数学)・英語だけでなく、理科や社会といった教科も選択することができます。
出席扱いを希望する場合は、主要教科だけに偏らず、できるだけ5教科すべてをバランスよく学ぶことが理想です。
自治体によっては、特定の教科だけの学習では出席扱いと認められないケースもあるため、すららの「全教科対応型」の強みを活かし、まんべんなく取り組むことがポイントです。
週単位・月単位で進捗を確認しながら、偏りがないよう工夫しましょう。
注意点4・学校との定期的なコミュニケーションが必要
出席扱いの申請を進めて承認を得た後も、継続的な「学校との関わり」は非常に大切です。
学校が出席扱いとして継続認定するには、「学習が続いているか」「どのような進捗か」などの情報を、家庭と共有し続ける必要があるためです。
保護者と担任との信頼関係が構築されていると、申請内容の信頼性も高まり、次年度以降の継続申請にもプラスに働きます。
月1回の進捗レポートの提出や、必要に応じた面談の実施など、負担にならない範囲で連絡を取り合うようにしましょう。
出席扱いにするためには、「学校と家庭で学習状況を共有」することが条件になることが多い
学校は「本当に家庭で学習が行われているか」を把握する必要があります。
そのため、家庭と学校の間で学習状況を定期的に共有し合う仕組みを作っておくことが求められます。
すららで自動生成されるレポートを活用すれば、その手間を大幅に省くことができます。
月に1回は学習レポートを提出(すららでダウンロードできる)すると良い
すららのマイページから出力できる学習レポートは、学習時間・単元・正解率などがグラフ付きで可視化されています。
これを月1回学校に提出することで、担任や教頭が学習の継続性を確認しやすくなり、信頼性の高い情報として扱われます。
学校から求められた場合は、家庭訪問や面談にも対応する
一部の学校では、実際の家庭学習の様子や子どもの状態を把握するために、家庭訪問や面談を希望することもあります。
可能であれば前向きに対応し、「協力的な姿勢」を見せることで、学校側の印象が良くなり、出席扱いに対する理解も深まる傾向があります。
担任の先生とは、こまめにメールや電話で進捗共有をすると良い
メールや電話での定期的なやり取りは、学校側との信頼関係を築くうえで非常に効果的です。
月ごとの学習進捗を一言伝えるだけでも、「継続的に取り組んでいる家庭」という安心感を与えられます。
担任もサポートしやすくなり、出席扱いの継続にもつながります。
注意点5・教育委員会への申請が必要な場合もある
地域によっては、出席扱いの最終承認に教育委員会の判断が必要なケースがあります。
学校だけではなく、自治体のガイドラインに沿った申請が求められる場合、保護者が個別に資料を用意しなければならないこともあります。
その際は学校としっかり連携し、教育委員会が求めるフォーマットや書類内容を確認しておくことが重要です。
すららでは、出席扱い申請の実績や書類提出のサポートも充実しているため、必要があればコーチに相談することでスムーズな対応が可能になります。
教育委員会向けの資料準備も、学校と相談しながら進める
教育委員会への申請が必要な場合、学校側が窓口となってくれることが多いですが、保護者としても事前に必要書類や申請の流れを把握しておくと安心です。
すららの学習記録や進捗データは、自治体にも提出可能な形で出力できるため、積極的に活用していきましょう。
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いを認めてもらうための成功ポイントを解説
不登校の子どもが「出席扱い」を得るためには、ただ学習しているだけでなく、学校側に納得してもらえる“伝え方”や“工夫”が重要になります。
すららは文部科学省のガイドラインに準じた教材であり、実際に多くの学校で出席扱いが認められていますが、その認定を引き出すためには、いくつかの“成功のコツ”を押さえておくことがとても大切です。
ここでは、すららを利用して出席扱いを得る際に、実際に効果があったと言われる具体的なアプローチ方法や提案の仕方をご紹介します。
ポイント1・学校に「前例」をアピールする
学校がすららを知らなかったり、出席扱いの申請が初めての場合、「前例があること」を伝えるだけで、ぐっと話が通りやすくなります。
すららは全国の多くの学校や自治体で導入されており、すでに出席扱いを認めた実績が多数あります。
学校側にとっても、前例のある教材ということで安心感が増し、「判断しやすい」と感じてもらえるのです。
最初の説明の段階で、前例の情報を具体的に提示しておくことで、前向きな対応を引き出すきっかけになります。
「すららで出席扱いになった他の学校」の事例を学校に紹介すると効果的
すららを使った出席扱いの成功例は公式サイトでも紹介されており、「◯◯県の△△中学校で認められた」というような具体例を伝えると、説得力が増します。
「うちの学校でもできそう」と思ってもらえるかが鍵です。
すららの公式サイトに実績紹介があるので、それをプリントして持参する
学校との面談時には、すららの出席扱い事例が掲載されたページを印刷して持っていくとベストです。
公式情報として提示できるので、話の信ぴょう性が増し、説明がスムーズに進みます。
ポイント2・「本人のやる気」をアピール
学校側が出席扱いを認めるかどうかを判断する際、最も重視するのが「本人の意思」です。
「親が頑張っている」だけではなく、「本人に学ぶ意欲があること」をしっかり伝えることで、学校側も「この子を支援したい」と前向きに捉えてくれやすくなります。
すららは自分のペースで学べるため、本人が主体的に取り組みやすい教材です。
その特性を活かして、本人の気持ちを積極的に学校に届けていきましょう。
本人が書いた学習の感想や目標を提出すると良い
「すららを使って〇〇が分かるようになった」「将来〇〇になりたいから頑張りたい」といった短い感想文でもOKです。
手書きのメモや目標リストがあるだけで、本人の意欲が伝わります。
面談がある場合は、本人も参加して「頑張っている」と伝えると良い
学校との面談には可能であれば本人も同席し、自分の言葉で「続けたい」「勉強している」と伝えることで信頼感が大きくなります。
難しければ、動画や音声メッセージでもOKです。
ポイント3・「無理なく、継続可能な学習計画」を立てる
すららで出席扱いを得るためには、毎日の学習が「継続されていること」が何より大切です。
どれだけ最初に頑張っても、それが一時的なものだと判断されれば、継続的な学習支援とはみなされません。
そこで大事なのが、「無理のない、本人に合ったスケジュール」を立てることです。
気持ちが落ち込んでいるとき、体調が優れないときでも、できる範囲で継続できるよう、柔軟で現実的な学習計画を設計しておきましょう。
継続が最重要だから、本人に合わせた計画が必須となる
毎日30分でもいいので、途切れずに続けることが一番大切です。
やる気に波があるお子さんでも、無理なく習慣にできるように工夫しましょう。
最初は少なめの計画からスタートして、徐々に増やすのも効果的です。
すららコーチに相談して、現実的なスケジュールを一緒に立ててもらう
すららには学習スケジュールを一緒に立ててくれる「すららコーチ」がついています。
子どもの性格や特性を考慮して、現実的な学習プランを提案してもらえるので、無理なく続けるための大きな支えになります。
ポイント4・「すららコーチ」をフル活用する
すららの最大の特長の一つが、「すららコーチ」の存在です。
出席扱いの申請や継続に必要な学習レポートや証明書の発行、学習の進捗管理、スケジュールの調整など、すべてを保護者と二人三脚でサポートしてくれます。
出席扱いに関する相談にも慣れており、どんな資料が必要か、いつ提出すべきかなども丁寧に教えてくれるため、心強い味方になってくれます。
わからないことがあれば、まずコーチに相談してみるのが成功の第一歩です。
出席扱いのために必要なレポート作成や学習証明はコーチがサポートしてくれる
学習レポートの作成やダウンロード、出席扱い申請のタイミング、書類の提出方法など、すべての工程をコーチがフォローしてくれます。
家庭だけでは不安な部分も、コーチが入ってくれることで安心感がまるで違います。
すららは不登校でも出席扱いになる?実際に利用したユーザーや子供の口コミ・評判を紹介します
すららは、不登校の子どもにとって大きな支えになるオンライン教材として注目されています。文部科学省の「出席扱い制度」を利用すれば、自宅での学習が学校の出席日数に認められる場合があり、その対象教材としてすららが導入されるケースもあります。
学校や教育委員会との連携が必要ですが、条件を満たせば「出席扱い」として認められるのは、不登校の子どもや保護者にとって大きな安心材料です。
実際に利用した家庭からは「不登校でも学習の遅れを取り戻せた」「先生に相談して出席扱いになったので安心した」といった口コミも寄せられています。
また、子ども自身からも「学校に行けなくても勉強が続けられるから自信がついた」という声が聞かれます。学習の継続と心の安定を支えるすららは、不登校家庭にとって心強い選択肢のひとつになっています。
良い口コミ1・うちの子は中2から不登校になり、内申点が心配でした。でも、すららで学習を続けたことで「出席扱い」にしてもらえました
良い口コミ2・ 学校に行けなくなってから勉強が完全に止まってたけど、すららを始めて「毎日ちょっとずつやればいい」と思えた。時間も自分で決められるし、誰にも急かされないからストレスがない
良い口コミ3・ 不登校になってから、家で何もせずにゲームばかり。イライラして何度も怒ってしまっていましたが、すららを導入してから、1日10分でも学習に取り組むようになって、家庭の雰囲気がかなり良くなりました
良い口コミ4・ 小学校の時から算数が苦手で、それが原因で不登校になったけど、すららはアニメで説明してくれるし、ゆっくり復習できたので、だんだん分かるようになった
良い口コミ5・すららを始めて半年経った頃、子どもが「学校の授業も分かりそう」と言い出しました。完全に無理だと思ってた登校が、部分登校からスタートできました
悪い口コミ1・ 低学年だと、すららを一人で操作するのが難しくて、結局親がつきっきり。タブレットを使った勉強というより、「親子で一緒にやるドリル」みたいになってしまいました
悪い口コミ2・最初は頑張ってたけど、やっぱり「一人でやる」ことに飽きてしまいました。キャラが励ましてくれるのも、最初は嬉しかったけど、そのうち「うざい」と感じてしまった
悪い口コミ3・すららで学習は続けていたものの、学校が「出席扱い」を認めてくれませんでした。教育委員会にも相談しましたが、地域によって判断が違うのが辛かった
悪い口コミ4・続ければ続けるほど料金が積み上がっていくので、経済的にきつくなってきました。他のオンライン教材よりは高めの印象。
悪い口コミ5・勉強にブランクがあったので仕方ないけど、「すららをやってすぐに成績が上がる!」ってわけではなかったです
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?についてのよくある質問と回答
すららを利用しているご家庭からよく寄せられる質問のひとつに「不登校でも出席扱いになるのですか?」というものがあります。
結論から言うと、すららを利用しているだけで自動的に出席扱いになるわけではありません。出席扱いにするかどうかは最終的に学校や教育委員会の判断に委ねられるため、地域や学校によって対応が異なります。
ただし、文部科学省の通知でICT教材を活用した学習も出席扱いとして認められる可能性があると示されており、実際にすららを利用して出席扱いが認められた事例もあります。そのため、まずは学校に相談し、担任や校長先生と話し合いながら「学習計画の提出」や「学習記録の共有」を行うことが重要です。
すららは家庭で無理なく学習を続けられる仕組みが整っているため、不登校のお子さんにとって大きな支えとなります。正しい手続きを踏めば、出席扱いが認められる可能性を広げられるのです。
すららはうざいという口コミがあるのはどうしてでしょうか?
すららに対して「うざい」という口コミがある理由には、さまざまな背景があります。
例えば「自分で学習管理をしないと進まないので大変」「最初は楽しくても途中で飽きてしまう」「保護者への連絡が多く感じた」などが挙げられます。
ただし、これらは受け手側の学習スタイルや生活リズムに合わなかった場合が多く、逆に「子どもが前向きに取り組めた」「無理のない学習で続けやすい」といった好意的な声も多いのが事実です。
教材自体に問題があるというよりも、「合う・合わない」が口コミに反映されている印象です。
関連ページ:【すらら】はうざい!?小中高の料金や最悪の噂は?タブレット教材の口コミを比較
すららの発達障害コースの料金プランについて教えてください
すららには明確に「発達障害コース」という名称はありませんが、発達障害や学習障害を持つお子さまでも使いやすい構成となっており、専門性の高いサポートが充実しています。
ADHD・ASD・LDなど特性に応じて、学習の進め方を個別に調整してくれる「すららコーチ」が付いており、親子の負担が軽くなるのも大きなメリットです。
料金は他の利用者と同じで、入会金と月額費用のみ。
割引制度などは用意されていませんが、サポートの質が高いためコスパの面では非常に好評です。
関連ページ:すららは発達障害の料金が安くなる?学習障害や慮育手帳を持っている人の料金は?
すららのタブレット学習は不登校の子供でも出席扱いになりますか?
すららは、不登校のお子さんが「出席扱い」として認められるための教材として、全国の多くの学校や教育委員会で利用されています。
文部科学省が定める「出席扱い要件」に沿って開発された教材であり、学習の進捗レポートや学習記録が自動で保存・出力できる点が評価されています。
学校と家庭で協力し、すららのレポートを定期的に提出することで、出席扱いとして認定されるケースが増えています。
特に「無学年式」で学習できる点や、コーチの支援があることも安心材料のひとつです。
関連ページ:すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの申請手順・注意点・成功のポイントについて
すららのキャンペーンコードの使い方について教えてください
すららでは、キャンペーンコードを使うことで入会金が無料になったり、初月の受講料が割引になったりすることがあります。
キャンペーンコードは、すらら公式サイトの案内や提携サイト・口コミブログなどで配布されています。
入会申し込みの際、申し込みフォームにある「キャンペーンコード」欄に正確に入力するだけで簡単に適用されます。
使用期限や対象コースに注意しながら、早めの利用がベストです。
複数のキャンペーンが重なることはないため、最新情報をよく確認しましょう。
関連ページ:すららのキャンペーンコードの入手方法は?入会無料の特典について
すららの退会方法について教えてください
すららの退会には2つのステップがあります。
「解約」は利用を停止し、月額の課金を止める手続き、「退会」はアカウントごとデータを削除する手続きです。
どちらも電話での対応が必要で、WEBやメールでは受け付けていません。
電話では本人確認(登録者の氏名やIDなど)を行ったうえで、解約希望日を伝えます。
退会は、解約後に希望があればそのまま申し出ることで手続き可能です。
再開の予定がある方は解約のみでOK。
電話対応は丁寧なので、安心して連絡してみてください。
関連ページ:すららの退会手続き・方法について解説します/解約・休会はいつまでにする?
すららは入会金と毎月の受講料以外に料金はかかりますか?
すららでは、基本的に「入会金+月額の受講料」のみで利用できます。
教材費や追加機能の費用、サポート料金などは一切かかりません。
学習はパソコンやタブレットを使って進めるため、専用の教材購入や印刷費なども不要です。
ただし、インターネット環境と端末の準備は家庭で行う必要があります。
すらら専用端末の販売やレンタルなども行っていないため、お手持ちのタブレットやPCが推奨環境に対応しているかどうか事前に確認しておくと安心です。
1人の受講料を支払えば兄弟で一緒に使うことはできますか?
すららは、1人ひとりの学習履歴・進捗・弱点などをAIが分析しながらサポートするシステムです。
そのため、1つの契約で兄弟が一緒に使うことはできません。
それぞれに個別のIDと学習環境が必要になるため、兄弟が利用する場合は人数分の契約が必要です。
ただし、同時に申し込むと「兄弟割引」が適用されることもあり、2人目以降の入会金が免除になるケースもあります。
兄弟それぞれが自分のペースで無理なく進められるのは、すららの大きな魅力のひとつです。
すららの小学生コースには英語はありますか?
はい、すららの小学生コースには英語の学習コンテンツが含まれています。
英語に初めて触れるお子さまでも安心して取り組める内容になっており、音声やアニメーションを活用しながら楽しく基礎を学べる構成です。
フォニックスや英単語、簡単な会話文などを段階的に学び、「聞く・読む・話す・書く」の4技能をバランスよく伸ばす工夫が詰まっています。
中学校の英語学習への橋渡しにもなる内容で、英語に対する苦手意識を持たせず、自然に親しむことができます。
すららのコーチからはどのようなサポートが受けられますか?
すららには、学習者1人ひとりを担当する「すららコーチ」がいます。
コーチは、お子さまの学習状況をチェックし、適切な学習計画を立ててくれたり、進捗が遅れている場合にやさしくサポートしてくれたりします。
不登校や発達障害など個別の事情に対しても理解があり、保護者と連携しながら無理のない学び方を提案してくれるのが魅力です。
また、学習のつまずきがあった場合にもアドバイスをくれるため、親子だけで悩まずに続けていける心強い存在です。
参照:よくある質問(すらら公式サイト)
【すらら】は不登校でも出席扱いになる?他の家庭用タブレット教材との違いを比較しました
不登校の背景には、発達特性や心の不調など、さまざまな理由があります。
だからこそ、タブレット教材も「出席扱いになるかどうか」だけでなく、「子どもが無理なく続けられるか」が重要ですよね。
この記事では、すららを中心に、Z会、スマイルゼミ、スタディサプリなどの主要教材と比較し、それぞれの向き・不向きを解説しています。
学習のしやすさ、サポートの手厚さ、家庭での管理のしやすさなど、親子の負担を減らす視点で比べているので、教材選びに迷っている方にぜひ読んでいただきたい内容です。
| サービス名 | 月額料金 | 対応年齢 | 対応科目 | 専用タブレット |
| スタディサプリ小学講座 | 2,178円~ | 年少~6年生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| RISU算数 | 2,680円~ | 年中~6年生 | 算数 | 必須 |
| スマイルゼミ小学生コース | 3,278円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | 必須 |
| すらら | 8,800円~ | 1年~高校3年 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| オンライン家庭教師東大先生 | 24,800円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| トウコベ | 20,000円~ | 小学生~浪人生 | 国語、算数、理科、社会、英語 | ✖ |
| 天神 | 10,000円~ | 0歳~中学3年 | 国語、算数、理科、社会、音楽、図画工作 | 必須 |
| デキタス小学生コース | 3,960円~ | 小学1年~6年 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| DOJO学習塾 | 25,960円~ | 小学生~中学生 | 漢字・語い・英単語・計算 | 必須 |
| LOGIQ LABO(ロジックラボ) | 3,980円~ | 小学1年~6年 | 算数、理科 | ✖ |
| ヨミサマ。
|
16,280円~ | 小学4年~高校生 | 国語 | ✖ |
| 家庭教師のサクシード | 12,000円~ | 小学生~高校生 | 国語、算数、理科、社会 | ✖ |
| ヨンデミー | 2,980円~ | なし | 読書 | ✖ |
すららは不登校でも出席扱いになる?出席扱いの制度・注意点・申請手順まとめ
不登校の子どもに「学びの場」を提供する一方で、「学校との関係がうまくいっていない」「出席扱いをお願いするのが気まずい」と感じている保護者の方も多いかもしれません。
この記事では、すららを使った出席扱いの申請制度について、仕組みから申請の流れ、学校への説明方法、注意点まで詳しくまとめています。
無理なく制度を活用し、学校との関係をこじらせないための工夫も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
すららコーチのサポートを活用することで、申請のハードルもぐっと下がりますよ。