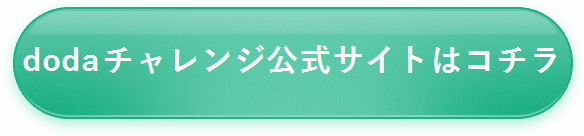dodaチャレンジで断られた!?断られる人の特徴や断られた理由について解説します

dodaチャレンジは、障がい者向けの転職支援サービスとして、多くの求職者に利用されています。
しかし、中には「登録しようとしたら断られた」「求人紹介を受けられなかった」というケースもあります。
なぜdodaチャレンジで断られてしまうのか?その理由にはいくつかのパターンがあります。
ここでは、dodaチャレンジで断られる主な理由や、どのような人がサポートを受けにくいのかについて詳しく解説します。
断られる理由1・紹介できる求人が見つからない
dodaチャレンジでは、求職者の希望やスキルに合った求人を紹介していますが、条件が厳しすぎたり、対象となる求人が少なかったりすると、「紹介できる求人が見つからない」として断られることがあります。
希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、フルフレックス、年収500万円以上など)
最近は在宅勤務の求人も増えてきていますが、完全在宅の求人はまだ限られています。
フルリモート勤務やフルフレックスなどの柔軟な働き方を希望する場合、dodaチャレンジで紹介できる企業が少なくなり、マッチングが難しくなることがあります。
また、障がい者雇用枠では、年収が比較的低めに設定されることが多いため、年収500万円以上などの高年収を希望すると、対象となる求人がほとんどなくなってしまう可能性があります。
希望職種や業種が限られすぎている(クリエイティブ系、アート系など専門職など)
クリエイティブ職やアート系の職種は、一般の求人市場でも募集が少なく、特に障がい者雇用枠での募集はかなり限られています。
また、専門職は即戦力が求められることが多く、未経験者やスキルが不十分な場合は、紹介できる求人が見つからないこともあります。
そのため、特定の職種にこだわる場合は、dodaチャレンジ以外の専門職向け転職エージェントの活用も検討する必要があります。
勤務地が限定的(地方で求人自体が少ない)
dodaチャレンジの求人は、首都圏・関西圏・中部圏などの大都市圏に集中している傾向があります。
そのため、地方在住で「地元で働きたい」と考えている場合、紹介できる求人が少なく、登録を断られてしまうことがあります。
特に、地方の中小企業では、障がい者雇用の受け入れ体制が整っていないことが多く、選択肢が限られるのが現実です。
そのため、勤務地にこだわる場合は、地元のハローワークや地方自治体の障がい者就職支援サービスを活用するのも一つの方法です。
断られる理由2・サポート対象外と判断される場合
dodaチャレンジは、障がい者雇用枠での転職支援を専門に行っているため、一定の基準に合致しない場合はサポート対象外となることがあります。
障がい者手帳を持っていない場合(障がい者雇用枠での求人紹介は、原則手帳が必要)
dodaチャレンジで紹介される求人の多くは、「障がい者雇用枠」での募集です。
このため、原則として障がい者手帳を持っていることが求められます。
一部の企業では、医師の診断書や通院履歴があれば応募できるケースもありますが、基本的には障がい者手帳が必要とされるため、持っていない場合は登録を断られることがあります。
もし障がい者手帳を取得できる可能性がある場合は、役所で手続きの方法を確認し、取得を検討するのも良いでしょう。
長期間のブランクがあって、職務経験がほとんどない場合
長期間のブランクがある場合や、これまでの職務経験がほとんどない場合、企業側が「即戦力としての採用が難しい」と判断し、マッチングが成立しにくくなることがあります。
特に、障がい者雇用枠の求人は、企業が求める業務内容に対して最低限のスキルや経験を持っていることが前提となるケースが多いため、全くの未経験者に対しては紹介できる求人が少なくなる可能性があります。
このような場合は、職業訓練を受けたり、アルバイトや契約社員から経験を積んだりすることで、就職の可能性を広げることができます。
また、障がい者向けの職業訓練プログラムやハローワークの支援を活用するのもおすすめです。
状が不安定で、就労が難しいと判断される場合(まずは就労移行支援を案内されることがある)
dodaチャレンジでは、求職者の健康状態や就労の継続が可能かどうかも考慮されます。
特に、体調が安定しておらず、フルタイムでの勤務が難しいと判断される場合は、すぐに求人の紹介が難しいことがあります。
このような場合、dodaチャレンジのキャリアアドバイザーから、「まずは就労移行支援を利用して職場復帰の準備をするのが良い」といったアドバイスを受けることもあります。
就労移行支援では、仕事に必要なスキルのトレーニングや、模擬業務を通じて働く準備をすることができます。
体調の安定や働く自信をつけた上で、改めて転職活動を行うことで、より良いマッチングが期待できます。
断られる理由3・面談での印象・準備不足が影響する場合
dodaチャレンジでは、キャリアアドバイザーとの面談を通じて、求職者の希望や適性を把握します。
しかし、面談時の準備不足や説明の仕方によっては、求人を紹介してもらえないこともあります。
障がい内容や配慮事項が説明できない
障がい者雇用枠での転職活動では、自分の障がいの特性や、どのような配慮が必要かを企業に伝えることが重要になります。
面談の際に「どんな業務ならできるのか?」「どのような環境なら働きやすいのか?」を明確に伝えられないと、企業側も採用を判断しづらくなります。
キャリアアドバイザーに相談しながら、事前に整理しておくことが大切です。
どんな仕事をしたいか、ビジョンが曖昧
「とにかく何でもいいから働きたい」「特に希望職種は決まっていない」といった状態では、適切な求人を紹介するのが難しくなります。
dodaチャレンジでは、求職者の希望をもとに求人を探すため、「どんな仕事をしたいのか?」「どんな働き方を希望するのか?」を明確にしておくことが大切です。
もし希望職種が決まっていない場合でも、過去の経験や興味のある分野について整理しておくと、キャリアアドバイザーが適切な求人を提案しやすくなります。
職務経歴がうまく伝わらない
面談で職務経歴を説明するときに、具体的な業務内容や実績を伝えられないと、アドバイザーが適切な求人を選ぶのが難しくなります。
例えば、「事務職をしていました」とだけ伝えるのではなく、「データ入力や書類作成、電話対応などを担当していました」と具体的に説明することで、キャリアアドバイザーが求人を紹介しやすくなります。
また、過去の職歴が少ない場合は、ボランティア活動や学校での経験などもアピールポイントになります。
事前に職務経歴を整理し、どのように説明するか準備しておくのがおすすめです。
断られる理由4・地方エリアやリモート希望で求人が少ない
dodaチャレンジは全国対応の転職支援サービスですが、地域によっては求人が少ないことがあります。
特に、地方在住の方や完全在宅勤務を希望する方は、選択肢が限られるケースが多いです。
地方在住(特に北海道・東北・四国・九州など)
首都圏や大都市圏では、障がい者雇用枠の求人が比較的多くありますが、地方では求人数が限られるため、希望する職種や条件に合う仕事が見つかりにくくなります。
特に、北海道・東北・四国・九州などの地方では、求人の選択肢が少なく、「勤務地を広げる」「通勤できる範囲を見直す」といった対策をとることで、転職の可能性が高まることがあります。
完全在宅勤務のみを希望している場合(dodaチャレンジは全国対応ではあるが地方によっては求人がかなり限定される)
近年、リモートワークが普及しつつありますが、完全在宅勤務のみの求人はまだまだ少ないのが現状です。
特に、障がい者雇用枠では「オフィスに出社できること」を前提としている企業が多いため、「フルリモート勤務希望」とすると、紹介できる求人が大幅に減る可能性があります。
そのため、「週に数回の出社が可能か?」「フレックスタイム制の求人も検討できるか?」といった柔軟な条件を設定することで、求人の幅を広げることができます。
断られる理由5・登録情報に不備・虚偽がある場合
dodaチャレンジの登録時に、入力した情報に不備や虚偽があると、求人の紹介を受けられないことがあります。
登録情報が正確でないと、キャリアアドバイザーが適切な求人を紹介できず、最悪の場合、サポートの対象外となることもあります。
手帳未取得なのに「取得済み」と記載してしまった
障がい者雇用枠の求人は、障がい者手帳を持っていることが前提となるケースがほとんどです。
そのため、手帳を未取得の状態で「取得済み」として登録すると、実際の求人応募時に企業側とのミスマッチが発生し、トラブルの原因になることがあります。
dodaチャレンジの登録前に、まずは障がい者手帳の取得が可能かどうかを確認し、取得予定であれば「申請中」など正しい情報を記載することが大切です。
働ける状況ではないのに、無理に登録してしまった
健康状態が安定しておらず、就労が難しい状況にもかかわらず無理に登録した場合、キャリアアドバイザーから「今すぐの転職活動は難しい」と判断されることがあります。
このような場合、dodaチャレンジ側から「まずは治療を優先する」「就労移行支援を活用する」などの提案を受けることもあります。
転職活動をスムーズに進めるためにも、無理に登録せず、働ける状態が整ってから登録することが重要です。
職歴や経歴に偽りがある場合
登録時に、職歴やスキルについて実際とは異なる内容を記載した場合、面談時にキャリアアドバイザーが事実と異なることを察知し、サポートが受けられなくなる可能性があります。
また、企業に応募する際に経歴の虚偽が発覚すると、内定取り消しのリスクもあるため、正直に自分の経歴を伝えることが大切です。
もしブランクがある場合は、その期間に行っていた活動(リハビリ、勉強、ボランティアなど)を記載することで、より前向きな印象を持たれやすくなります。
断られる理由6・企業側から断られるケースも「dodaチャレンジで断られた」と感じる
dodaチャレンジで求人を紹介されても、最終的に企業側の選考で不採用となることがあります。
この場合、「dodaチャレンジで断られた」と感じるかもしれませんが、実際には企業の選考基準によるものであり、エージェント側の判断とは異なります。
不採用は企業の選考基準によるもの
企業側が採用を決定する際には、以下のような基準をもとに判断されます。
– スキル・経験が求めるレベルに達していない
– 他の応募者と比較して、より適した人がいた
– 社風や業務内容とのマッチ度が低い
– 企業が想定する配慮ができないと判断された
不採用の理由は企業によってさまざまですが、必ずしも「能力不足」というわけではありません。
たとえ1社で不採用になったとしても、次のチャンスに向けて改善点を見つけ、前向きに転職活動を続けることが大切です。
dodaチャレンジでは、面接対策や書類添削のサポートも受けられるため、不採用が続く場合はキャリアアドバイザーに相談しながら改善策を考えることが重要です。
dodaチャレンジで断られた人の体験談/どうして断られたのか体験談や口コミを調査しました
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した転職支援サービスですが、すべての求職者に必ずしも求人を紹介できるわけではありません。
条件によっては「紹介できる求人がありません」と言われたり、サポートを受けられないこともあります。
実際にdodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった人の体験談を調査し、どのような理由で断られたのかをまとめました。
同じような状況の方は、改善策を考えながら転職活動を進める参考にしてみてください。
体験談1・障がい者手帳は持っていましたが、これまでの職歴は軽作業の派遣だけ。PCスキルもタイピング程度しかなく、特に資格もありません。紹介できる求人がないと言われてしまいました
dodaチャレンジでは、求職者のスキルや経験に基づいて求人を紹介しますが、事務職や専門職を希望する場合、最低限のPCスキルや業務経験が求められることが多いです。
特に、事務職の場合はExcelやWordの基本操作、メール対応などのスキルが必要となるため、未経験でこれらのスキルがないと求人の選択肢が限られてしまいます。
このような場合は、まず職業訓練やオンライン講座を利用して基本的なPCスキルを身につけると、紹介可能な求人の幅が広がる可能性があります。
体験談2・継続就労できる状態が確認できないため、『まずは就労移行支援などで安定した就労訓練を』と言われてしまいました。
dodaチャレンジでは、継続的に働ける状態であることが求められます。
そのため、体調が安定していない、過去に短期間で退職を繰り返している場合などは、まず就労移行支援を利用して安定した就労訓練を行うことを推奨されることがあります。
就労移行支援を受けることで、働くための体力やスキルを身につけ、就職後の定着率を高めることができます。
dodaチャレンジでの紹介を断られた場合でも、まずは支援機関を活用して準備を整えるのも選択肢の一つです。
体験談3・精神疾患で長期療養していたため、10年以上のブランクがありました。dodaチャレンジに相談したものの、『ブランクが長く、就労経験が直近にないため、まずは体調安定と職業訓練を優先しましょう』と提案されました
長期間のブランクがある場合、すぐに正社員としての求人紹介を受けるのは難しいケースがあります。
特に、直近の就労経験がない場合は、まず職業訓練や短時間勤務からスタートし、無理なく職場復帰できる環境を整えることが大切です。
また、ブランク期間中に何かしらの活動(資格取得、ボランティア、短期アルバイトなど)を行っておくと、企業側に対して前向きな姿勢をアピールしやすくなります。
体験談4・四国の田舎町に住んでいて、製造や軽作業ではなく、在宅でのライターやデザインの仕事を希望していました。dodaチャレンジからは『ご希望に沿う求人はご紹介できません』といわれました
地方在住で特定の職種(ライター・デザイナーなど)を希望すると、求人数が限られるため、紹介できる求人がないと言われることがあります。
特に、在宅ワーク希望の場合、完全在宅勤務の障がい者雇用枠はまだ少なく、選択肢が限られるのが現状です。
このような場合は、クラウドソーシングサービスを利用して仕事を受注したり、業務委託の仕事を探すなど、別の方法を検討するのも一つの手です。
体験談5・これまでアルバイトや短期派遣での経験ばかりで、正社員経験はゼロ。dodaチャレンジに登録したら、『現時点では正社員求人の紹介は難しいです』と言われました
正社員経験がない場合、即戦力としての採用が難しく、企業側も慎重になることがあります。
この場合は、まず契約社員や派遣社員として経験を積み、徐々に正社員を目指す方法を検討するのがおすすめです。
また、職業訓練やハローワークの支援を活用し、スキルを身につけながら転職活動を進めるのも良いでしょう。
体験談6・子育て中なので、完全在宅で週3勤務、時短勤務、かつ事務職で年収300万円以上という条件を出しました。『ご希望条件のすべてを満たす求人は現状ご紹介が難しいです』と言われ、紹介を断られました
希望条件が厳しすぎると、紹介できる求人がないと言われることがあります。
特に、完全在宅勤務・時短勤務・高収入を同時に満たす求人は非常に少ないため、条件を柔軟にすることが大切です。
例えば、最初は短時間のリモートワークからスタートし、徐々に働く時間を増やしていくなど、段階的なキャリアプランを考えると、転職の選択肢が広がります。
体験談7・精神障がい(うつ病)の診断を受けていますが、障がい者手帳はまだ取得していませんでした。dodaチャレンジに登録を試みたところ、『障がい者手帳がない場合は求人紹介が難しい』と言われました
dodaチャレンジでは、基本的に障がい者手帳を持っている人を対象に求人を紹介しています。
そのため、手帳がない状態では、応募できる求人が限られるか、紹介を受けられないことがあります。
手帳を取得する予定がある場合は、キャリアアドバイザーに相談し、手続きの進捗を伝えることで、対応が変わる可能性があります。
また、一般枠での就職活動も視野に入れることで、より多くの選択肢を持つことができます。
体験談8・長年、軽作業をしてきたけど、体調を考えて在宅のITエンジニア職に挑戦したいと思い、dodaチャレンジに相談しました。『未経験からエンジニア職はご紹介が難しいです』と言われ、求人は紹介されませんでした
エンジニア職は、在宅勤務が可能な求人も多いですが、障がい者雇用枠では即戦力が求められるケースが多く、実務未経験の状態では求人の紹介が難しいことがあります。
この場合、まずは基礎的なプログラミングスキルを身につけることが大切です。
オンラインの無料学習サイトやハローワークの職業訓練を活用して、HTML・CSS・JavaScriptなどの基礎を学び、ポートフォリオを作成すると、未経験でも応募できる求人が増える可能性があります。
また、エンジニア職は企業によって求めるスキルが異なるため、どの分野(Web開発、システム開発、インフラなど)に進みたいのかを明確にすることも重要です。
体験談9・身体障がいで通勤も困難な状況で、週5フルタイムは無理。短時間の在宅勤務を希望しましたが、『現在ご紹介できる求人がありません』と断られました
障がい者雇用枠の求人は、オフィス勤務が前提となっているものが多いため、完全在宅の短時間勤務の求人は非常に限られています。
このような場合、リモートワークを中心に取り扱う転職エージェントや、クラウドソーシングサイトを活用するのもひとつの方法です。
特に、事務職・ライティング・デザイン・プログラミングなどの仕事は、フリーランスや業務委託の求人も多いため、選択肢が広がります。
また、在宅勤務可能な企業で「最初はオフィス勤務が必要」となっている場合でも、入社後に在宅勤務へ移行できるケースもあるため、キャリアアドバイザーに相談してみるのもおすすめです。
体験談10・前職は中堅企業の一般職だったけど、今回は障がい者雇用で管理職や年収600万以上を希望しました。dodaチャレンジでは『ご紹介可能な求人は現在ありません』と言われました
障がい者雇用枠では、管理職ポジションや高年収の求人は非常に少なく、一般的な事務職や専門職が中心となっています。
そのため、一般職からいきなり管理職を目指す場合、該当する求人がほとんど見つからないことがあります。
この場合は、まずはリーダー職やマネージャー候補として働きながら、徐々に管理職を目指す方法を検討するとよいでしょう。
また、年収アップを希望する場合は、スキルを証明できる資格(MBA、プロジェクトマネジメント資格など)を取得することで、キャリアの幅を広げることができます。
dodaチャレンジで断られたときの詳しい対処法について紹介します
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合、すぐに諦める必要はありません。
スキルを磨いたり、他の転職サービスを活用することで、新たなチャンスを見つけることができます。
ここでは、dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった理由別に、具体的な対処法を紹介します。
スキル不足・職歴不足で断られたとき(職歴が浅い、軽作業や短期バイトの経験しかない、PCスキルに自信がないなど)の対処法について
スキル不足や職歴の浅さが理由で求人を紹介してもらえなかった場合、まずは職業訓練や資格取得を通じて、スキルアップを図ることが重要です。
ハローワークの職業訓練を利用する/ 無料または低額でPCスキル(Word・Excel・データ入力など)が学べる
ハローワークでは、求職者向けに無料または低額で受講できる職業訓練を提供しています。
特に、事務職を希望する場合は、WordやExcelのスキルを習得することで、応募できる求人の幅が広がります。
就労移行支援を活用する/実践的なビジネススキル、ビジネスマナー、メンタルサポートも受けられる
就労移行支援では、実際の職場を想定した業務トレーニングや、メンタル面のサポートを受けながら、働くための準備ができます。
職業訓練と組み合わせて活用することで、より安定した就職が可能になります。
資格を取る/MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級があると、求人紹介の幅が広がる
資格を取得することで、スキルを客観的に証明でき、企業側も安心して採用を検討しやすくなります。
特に、事務職を希望する場合は、MOS(Microsoft Office Specialist)や日商簿記3級を取得すると、応募できる求人が増える可能性があります。
ブランクが長すぎてサポート対象外になったとき(働くことへの不安が強い、数年以上の離職や療養期間があるなど)の対処法について
長期間のブランクがある場合、いきなり正社員での復職を目指すよりも、段階的に働くことを意識することが大切です。
– 短時間のアルバイトやパートから始める
– 就労移行支援で職業訓練を受ける
– リワークプログラムを活用して、働くリズムを取り戻す
また、ブランク期間中に取り組んだこと(資格取得、ボランティア活動など)を履歴書に記載することで、企業に対して前向きな姿勢をアピールすることができます。
就労移行支援を利用して就労訓練をする/毎日通所することで生活リズムを整え、安定した就労実績を作れる
就労移行支援を活用することで、職業スキルを習得できるだけでなく、毎日通所することで生活リズムを整えることができます。
安定した就労実績を積むことで、再度転職活動を行う際にアピール材料として活用しやすくなります。
特に、長期間のブランクがある方や、働くことに対する不安がある方には、無理のない形で仕事復帰の準備ができるためおすすめです。
短時間のバイトや在宅ワークで「実績」を作る/週1〜2の短時間勤務から始めて、「継続勤務できる」証明をつくる
長時間勤務が難しい場合でも、週1〜2回の短時間勤務や在宅ワークから始めることで、少しずつ就労経験を積んでいくことができます。
継続的に働けることを証明できれば、転職活動を進める際に企業に対して「安定して働ける」というアピールがしやすくなります。
実習やトライアル雇用に参加する/企業実習での実績を積むと、再登録時にアピール材料になる
企業の実習プログラムやトライアル雇用制度を利用することで、実務経験を積むことができます。
実際の職場環境で働くことで、自分に合う仕事を見つけやすくなるだけでなく、転職活動の際に「実務経験あり」としてアピールすることが可能になります。
地方在住で求人紹介がなかったとき(通勤できる距離に求人が少ない、フルリモート勤務を希望しているなど)の対処法について
地方在住の場合、求人の選択肢が都市部に比べて少なくなりやすいため、複数の転職サービスを活用しながら柔軟に対応することが重要です。
在宅勤務OKの求人を探す/他の障がい者専門エージェント(atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレ)を併用
dodaチャレンジ以外にも、在宅勤務に特化した障がい者向けの転職サービスがあります。
atGP在宅ワーク、サーナ、ミラトレなどのエージェントを併用することで、より多くの在宅勤務可能な求人を見つけることができる可能性があります。
クラウドソーシングで実績を作る/ランサーズ、クラウドワークスなどでライティングやデータ入力の仕事を開始
フルリモートでの就労を希望する場合、クラウドソーシングを活用して実績を作るのも有効な手段です。
ライティングやデータ入力、プログラミングなど、自分のスキルに合った仕事を少しずつこなしていくことで、経験を積みながら収入を得ることができます。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークに相談する/地元密着型の求人情報が得られる場合がある
地方の求人は、全国展開している転職サービスではカバーしきれないことがあるため、地域密着型の就職支援機関を活用することも重要です。
地域の障がい者就労支援センターやハローワークでは、その地域ならではの求人情報を提供してくれることがあります。
希望条件が厳しすぎて紹介を断られたとき(完全在宅・週3勤務・年収◯万円など、条件が多いなど)の対処法について
求人紹介を断られる理由のひとつに、「希望条件が厳しすぎる」というケースがあります。
希望する条件を見直し、柔軟に調整することで、より多くの求人に応募できる可能性が高まります。
条件に優先順位をつける/「絶対譲れない条件」と「できれば希望」を切り分ける
転職活動を進める際、すべての希望を満たす求人を見つけるのは難しいことが多いです。
そのため、まずは「絶対に譲れない条件」と「できれば希望する条件」を切り分けることが大切です。
例えば、「完全在宅勤務」「週3勤務」「年収○万円以上」などの希望がある場合、それが本当に譲れないものなのかを整理するとよいでしょう。
希望が多すぎると求人が限られてしまうため、「リモートワークが可能であれば、週1〜2回の出社は可能」「最初は週4勤務で、慣れたら調整する」など、柔軟に考えることがポイントです。
譲歩できる条件はアドバイザーに再提示する/ 勤務時間、出社頻度、勤務地を柔軟に見直す
希望条件を明確にしたら、譲歩できる部分をアドバイザーに再提示し、求人の幅を広げる工夫をしましょう。
勤務時間や出社頻度、勤務地などを柔軟に見直すことで、紹介可能な求人が増える可能性があります。
例えば、「完全リモート」ではなく「週1〜2回の出社が可能」と伝えるだけで、対象の求人が大幅に増えることがあります。
また、勤務地を広げて通勤可能な範囲を再検討すると、より多くの企業の選考を受けられるようになります。
こうした調整をキャリアアドバイザーと相談しながら進めることで、自分に合った求人が見つかりやすくなります。
段階的にキャリアアップする戦略を立てる/最初は条件を緩めてスタート→スキルUPして理想の働き方を目指す
希望条件に合う求人が見つからない場合、まずは条件を少し緩めてスタートし、スキルアップをしながら理想の働き方を目指すという戦略もあります。
例えば、最初は希望年収より少し低めの求人に就き、経験を積みながら年収アップを狙う方法があります。
また、短時間勤務や契約社員から始めて、正社員登用や昇進を目指すことも可能です。
転職活動は一度きりではなく、キャリアを積み重ねていくものなので、最初の一歩として現実的な選択をすることが重要です。
手帳未取得・障がい区分で断られたとき(障がい者手帳がない、精神障がいや発達障がいで手帳取得が難航している、支援区分が違うなど)の対処法について
dodaチャレンジの障がい者雇用枠の求人は、基本的に障がい者手帳を持っていることが条件となっています。
そのため、手帳を取得していない場合や、取得の手続きが進んでいない場合は、別の方法を検討する必要があります。
主治医や自治体に手帳申請を相談する/ 精神障がい・発達障がいも条件が合えば取得できる
精神障がいや発達障がいのある人の中には、手帳を取得できることを知らなかったり、手続きが面倒に感じて申請をしていない人もいます。
しかし、手帳があることで応募できる求人の幅が広がるため、まずは主治医や自治体の福祉窓口に相談し、取得の可能性を確認することが重要です。
特に、精神障がい者保健福祉手帳は、診断書の内容や病歴によって取得できることがあります。
医師と相談しながら手続きの進め方を決めるのがよいでしょう。
就労移行支援やハローワークで「手帳なしOK求人」を探す/一般枠での就職活動や、就労移行後にdodaチャレンジに戻る
手帳を取得しないまま転職活動を進めたい場合は、一般枠での就職活動を検討するのも一つの方法です。
ハローワークや就労移行支援では、手帳がなくても応募できる求人を紹介してくれることがあります。
また、就労移行支援を利用して実績を積み、その後手帳を取得してからdodaチャレンジに再登録する方法もあります。
就労移行支援では、ビジネスマナーやPCスキルのトレーニングを受けながら、安定した職場への就職を目指すことができます。
医師と相談して、体調管理や治療を優先する/手帳取得後に再度登録・相談する
障がい者雇用枠での転職活動が難しい場合、まず体調管理や治療を優先し、安定した状態になってから手帳を取得し、再度転職活動を進めるのも一つの方法です。
手帳の取得には一定の診断期間や手続きが必要ですが、取得後は障がい者枠の求人に応募しやすくなるため、長期的に見て転職の選択肢を増やすことができます。
焦らずに自分のペースで準備を進めることが大切です。
その他の対処法/dodaチャレンジ以外のサービスを利用する
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合でも、他の転職サービスや支援機関を活用することで、新たなチャンスを見つけることができます。
例えば、障がい者向け転職エージェント(atGP、サーナ、アットジーピーなど)を活用すると、より多くの求人を紹介してもらえる可能性があります。
また、ハローワークや地域の就労支援機関に相談することで、地元の求人情報を得ることができるかもしれません。
複数の転職サービスを併用しながら、自分に合った働き方を探していくことが大切です。
dodaチャレンジで断られた!?発達障害や精神障害だと紹介は難しいのかについて解説します
dodaチャレンジは障がい者向けの転職支援サービスとして、多くの企業の求人を取り扱っています。
しかし、障がいの種類によっては、求人紹介が難しく感じるケースもあります。
特に、精神障害や発達障害のある方が「dodaチャレンジでは求人を紹介してもらえなかった」と感じることがあるようです。
このような状況が起こる背景には、企業側の受け入れ体制や合理的配慮の難しさが関係しています。
本記事では、身体障害、精神障害、発達障害を持つ方の就職事情について詳しく解説し、dodaチャレンジでの紹介が難しい場合の対策についても紹介します。
身体障害者手帳の人の就職事情について
身体障害者手帳を持つ方は、比較的求人が多く、就職しやすい傾向にあります。
これは、身体的な障がいは企業側にとって「合理的配慮を行いやすい」という特徴があるためです。
しかし、障がいの内容や等級によっては、就職の難易度が変わることもあります。
障害の等級が低い場合は就職がしやすい
身体障害者手帳を持っている方の中でも、軽度の障がい(等級が3級~6級程度)に該当する場合は、就職が比較的スムーズに進むことが多いです。
これは、企業側が配慮しやすく、通常の業務に支障が少ないと判断されるためです。
特に、軽度の上肢障がいや視力障がいなど、デスクワークに影響が少ない障がいの場合、一般の事務職やIT関連の仕事など、幅広い職種での採用が期待できます。
身体障がいのある人は、障がいの内容が「見えやすい」ことから、企業側も配慮しやすく採用しやすい傾向にある
身体障がいは、外見や診断書の情報から企業が状況を把握しやすく、どのような配慮が必要か明確にしやすいのが特徴です。
そのため、企業側も安心して採用を進めやすい傾向があります。
例えば、車いすを使用している場合、バリアフリーのオフィス環境を整えることで対応できます。
また、聴覚障がいの方には筆談やチャットツールを活用することで、業務に支障が出にくくなります。
企業側が合理的配慮を明確にしやすい(例:バリアフリー化、業務制限など)から、企業も安心して採用できる
合理的配慮とは、障がいのある方が働きやすい環境を提供するために企業が行う対応のことです。
身体障がいの場合、具体的な配慮がしやすいため、企業も受け入れに前向きになりやすいです。
例えば、バリアフリーのオフィスでの勤務や、通勤時間の調整、手話通訳者の配置などが挙げられます。
こうした配慮が整っている企業では、身体障がいを持つ方が長く安定して働ける環境が整っていることが多いです。
上肢・下肢の障がいで通勤・作業に制約があると求人が限られる
一方で、上肢や下肢に重度の障がいがある場合は、通勤や作業に制約が生じることがあります。
そのため、完全在宅勤務が可能な求人や、特定の業務に特化したポジションを探す必要があります。
特に、製造業や営業職など、身体を動かす仕事では採用が難しくなるため、デスクワーク中心の職種を選ぶことが重要です。
コミュニケーションに問題がない場合は一般職種への採用も多い
身体障がいがあっても、コミュニケーションに問題がなければ、一般職種への採用のチャンスが広がります。
特に、電話対応や対面での接客が求められない事務職や、IT系の仕事では、障がいの影響が少ないため、採用の可能性が高まります。
PC業務・事務職は特に求人が多い
身体障がいのある方の中でも、特に事務職やPC業務の求人は多くあります。
データ入力、経理、総務などの仕事は、障がいの影響を受けにくく、企業側も採用しやすい職種の一つです。
精神障害者保健福祉手帳の人の就職事情について
精神障害者保健福祉手帳を持つ方の就職は、身体障がい者とは異なる課題があります。
精神障がいは外見からは分かりにくく、症状の波があるため、企業側が受け入れに慎重になるケースが多いです。
また、合理的配慮が必要な場合でも、企業側がどのように対応すればよいか分からず、採用を控えることもあります。
そのため、精神障がい者の方がdodaチャレンジで求人を紹介してもらえないと感じることがあるのです。
次の項目では、精神障がい者の就職事情と、紹介が難しい理由について詳しく説明します。
症状の安定性や職場での継続勤務のしやすさが重視される
精神障がいや発達障がいを持つ方の就職では、企業側が「継続して働くことができるかどうか」を特に重視します。
これは、障がいの特性上、体調の波があったり、職場環境によって業務遂行が難しくなる場合があるためです。
そのため、企業としては「どの程度業務を任せられるのか」「どんな配慮が必要なのか」を慎重に判断する必要があります。
就職活動では、これまでの職歴や継続勤務の実績を示すことで、採用の可能性を高めることができます。
見えにくい障がいなので、企業が「採用後の対応」に不安を持ちやすいのが現実
精神障がいや発達障がいは、外見からは分かりにくいため、企業側が「どのように配慮すればよいのか」が分かりにくいのが現実です。
特に、過去に精神障がいのある社員を受け入れた経験がない企業では、対応方法に不安を感じ、採用を見送るケースもあります。
また、障がいの症状が個人によって異なるため、採用時の面接や書類選考の段階で「この方に合った配慮ができるのか」という点を企業が判断するのが難しいという問題もあります。
そのため、企業側が安心して採用できるように、求職者自身が「どんな配慮があれば働きやすいのか」を明確に伝えることが重要になります。
採用面接での配慮事項の伝え方がとても大切!
精神障がいや発達障がいを持つ方が就職活動をする際には、面接時の「配慮事項の伝え方」が非常に重要になります。
企業は、どのようなサポートが必要なのかを明確に知ることで、適切なポジションや業務内容を提案できるようになります。
例えば、「業務の指示は口頭よりも文書で伝えてもらえるとスムーズに対応できる」「静かな環境の方が集中しやすい」「ストレスがかかりすぎると体調を崩しやすい」など、自分の特性に合った配慮を伝えることで、企業側も採用の判断がしやすくなります。
また、「どのような配慮があれば安定して働けるか」を具体的に伝えることで、企業側の不安を和らげることができ、採用につながる可能性が高くなります。
療育手帳(知的障害者手帳)の人の就職事情について
知的障がいを持つ方は、療育手帳(知的障害者手帳)を取得することで、障がい者雇用枠での就職が可能になります。
しかし、知的障がいの程度によって、就職できる職種や就労環境が異なります。
一般企業での就職を希望する場合は、個々の能力や適性に合った仕事を見つけることが重要になります。
また、職場でのサポート体制や、業務の進め方が自分に合っているかどうかも、長く働くうえで重要なポイントになります。
療育手帳の区分(A判定 or B判定)によって、就労の選択肢が変わる
療育手帳には、知的障がいの程度によって「A判定(重度)」と「B判定(中軽度)」の2つの区分があります。
この区分によって、就職の選択肢や支援の内容が変わるため、どのような働き方が適しているのかを理解することが大切です。
A判定(重度)の場合、一般就労は難しく、福祉的就労(就労継続支援B型)が中心
A判定(重度)の場合、一般企業での就労は難しいことが多く、福祉的就労(就労継続支援B型)を利用するケースが多くなります。
就労継続支援B型は、企業での就労が難しい方向けの支援制度で、比較的負担の少ない作業を通じて、働くスキルを身につけることができます。
また、一部の企業では、知的障がいのある方でも働きやすい環境を整えているところもあります。
例えば、軽作業や清掃業務、シンプルな事務作業など、業務内容を明確に分けている企業では、A判定の方でも働きやすい環境が整っている場合があります。
B判定(中軽度)の場合、一般就労も視野に入りやすい
B判定(中軽度)の場合、一般企業での就職も十分に可能です。
特に、特別支援学校の卒業生や、就労移行支援を利用してトレーニングを受けた方は、企業での採用につながるケースが増えています。
企業側としても、比較的軽度の知的障がいであれば、業務をシンプルにすることで対応できるため、事務職や軽作業、製造業のライン作業などでの採用が見込めます。
B判定の方が一般就労を目指す場合は、自分の得意な作業や適性を理解し、企業側にアピールすることが大切です。
障害の種類と就職難易度について
障がいの種類によって、就職のしやすさや求人数が異なります。
一般的に、身体障がいの方は合理的配慮がしやすいため、比較的就職しやすい傾向があります。
一方で、精神障がいや発達障がいの場合は、企業側の受け入れ体制によって就職の難易度が変わることがあります。
また、知的障がいの方の場合は、障がいの程度によって一般就労が可能かどうかが異なります。
就職活動をする際には、自分の障がいの特性を理解し、適切な職種や企業を選ぶことが重要です。
次の項目では、障がいの種類ごとの就職難易度について詳しく解説します。
| 手帳の種類 | 就職のしやすさ | 就職しやすい職種 | 難易度のポイント |
| 身体障害者手帳(軽度〜中度) | ★★★★★★ | 一般事務・IT系・経理・カスタマーサポート | 配慮事項が明確で採用企業が多い |
| 身体障害者手帳(重度) | ★★ | 軽作業・在宅勤務 | 通勤や作業負担によって求人が限定 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | ★★ | 事務補助・データ入力・清掃・在宅ワーク | 症状安定と継続勤務が評価されやすい |
| 療育手帳(B判定) | ★★★★ | 軽作業・事務補助・福祉施設内作業 | 指導・サポート体制が整った環境で定着しやすい |
| 療育手帳(A判定) | ★★ | 福祉的就労(A型・B型) | 一般就労は難しく、福祉就労が中心になる場合が多い |
障害者雇用枠と一般雇用枠の違いについて
障害のある方が就職を考える際、障害者雇用枠での就職と一般雇用枠での就職のどちらを選ぶかは重要なポイントになります。
両者にはそれぞれメリット・デメリットがあり、自分の働き方に合った選択をすることが大切です。
障害者雇用枠は、企業が法律に基づき障がい者の雇用を促進するために設けている枠であり、障がいに配慮した環境が整っていることが多いです。
一方、一般雇用枠は、障害の有無に関係なく、すべての応募者が同じ条件で採用試験を受ける形になります。
それぞれの特徴を理解し、自分に合った働き方を見つけましょう。
障害者雇用枠の特徴1・企業が法律に基づき設定している雇用枠
障害者雇用枠とは、障害者雇用促進法に基づき、企業が一定の割合で障がい者を雇用するために設けている枠のことです。
企業には法定雇用率が定められており、この基準を満たすために障害者雇用枠を設けています。
障害者雇用枠で働く場合、企業は障害に対する合理的配慮を提供する義務があるため、勤務時間や仕事内容の調整、通院への配慮などを受けやすい環境が整っています。
そのため、無理なく働き続けることができるメリットがあります。
障害者雇用枠の特徴2・障害者雇用促進法により、民間企業は従業員の2.5%以上(2024年4月〜引き上げ)を障がい者として雇用するルールがある
日本では、障害者雇用促進法により、一定規模以上の企業は障がい者を雇用する義務があります。
2024年4月以降、民間企業における法定雇用率は2.5%に引き上げられ、大企業だけでなく中小企業にも障がい者の雇用が求められるようになっています。
この法定雇用率を達成できていない企業は、納付金の支払いが求められるため、積極的に障害者雇用枠を設ける企業が増えています。
そのため、障害者雇用枠での就職を希望する場合、企業側の受け入れ態勢が整っていることが多いです。
障害者雇用枠の特徴3・障害をオープンにし配慮事項を明確に伝えた上で雇用される
障害者雇用枠では、応募時に障害を開示することが前提となります。
そのため、企業側も応募者の障害特性を理解した上で採用活動を行い、必要な配慮を提供することが可能になります。
例えば、通院のために勤務時間を調整する、静かな環境で働けるように席を工夫する、業務の進め方を個別に調整するなど、具体的な配慮を受けることができます。
そのため、障がいに対するサポートを受けながら働きたい方にとっては、障害者雇用枠は安心して働ける環境になりやすいでしょう。
一般雇用枠の特徴1・障害の有無を問わず、すべての応募者が同じ土俵で競う採用枠
一般雇用枠は、障がい者に限らず、すべての応募者が平等に選考を受ける採用枠です。
そのため、応募時に障害を開示するかどうかは自由であり、健常者と同じ条件での選考が行われます。
障害者雇用枠と比べて求人数が多く、さまざまな業界・職種に挑戦できるメリットがあります。
しかし、採用後に障害に対する配慮を受けることが難しい場合もあり、自分にとって無理のない職場環境を選ぶことが重要です。
一般雇用枠の特徴2・障害を開示するかは本人の自由(オープン就労 or クローズ就労)
一般雇用枠で応募する場合、障害を開示するかどうかは本人の判断に委ねられます。
障害を開示して働く「オープン就労」と、開示せずに働く「クローズ就労」の選択が可能です。
オープン就労では、企業側が障害のことを理解しやすく、必要な配慮を受けられる場合があります。
一方、クローズ就労では、障害に関する特別な配慮は受けられませんが、通常の採用枠として応募できるため、求人数の幅が広がるというメリットがあります。
一般雇用枠の特徴3・基本的に配慮や特別な措置はないのが前提
一般雇用枠では、障害を開示しても、基本的には特別な配慮を受けることは期待できません。
企業側が障害者雇用を前提としていないため、業務内容や勤務条件が一般の社員と同じ基準で設定されることが多いです。
そのため、障害の特性によっては、働きづらさを感じる場合もあります。
特に、定期的な通院が必要な方や、特定の環境でしかパフォーマンスを発揮できない方は、事前に企業と十分に相談することが重要です。
年代別の障害者雇用率について/年代によって採用の難しさは違うのか
障害者の雇用率は、年代によって違いがあるのが特徴です。
特に、若年層(20代)は障害者雇用枠での採用が比較的多いのに対し、中高年層(40代以上)では就職が難しくなる傾向があります。
障害者雇用状況報告(2023年版)を元に紹介します
2023年の障害者雇用状況報告によると、障害者の雇用率は年々上昇傾向にあります。
しかし、年代別に見ると、20代・30代の若年層の採用率が高く、40代以上では求人数が減少する傾向が見られます。
これは、企業側が若年層の方が長期的に働ける可能性が高いと判断するためです。
そのため、40代以上の方は、スキルや経験をアピールしながら転職活動を進めることが重要になります。
| 年代 | 割合(障害者全体の構成比) | 主な就業状況 |
| 20代 | 約20~25% | 初めての就職 or 転職が中心。
未経験OKの求人も多い |
| 30代 | 約25~30% | 安定就労を目指す転職が多い。
経験者採用が増える |
| 40代 | 約20~25% | 職歴次第で幅が広がるが、未経験は厳しめ |
| 50代 | 約10~15% | 雇用枠は減るが、特定業務や経験者枠で採用あり |
| 60代 | 約5% | 嘱託・再雇用・短時間勤務が中心 |
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い
若年層(20〜30代)の雇用率は高く、求人数も多い障がい者雇用において、20〜30代の若年層は比較的採用されやすい傾向にあります。
企業側も「長期間働いてもらえる可能性が高い」という点を重視し、ポテンシャル採用や未経験者の育成枠を設けていることが多いです。
また、若年層向けの求人は、事務職や軽作業、IT関連など幅広い業種で募集されているため、選択肢が多いのも特徴です。
未経験者向けの研修制度が充実している企業も増えており、障がいがあっても安心して働き始められる環境が整っています。
20代や30代であれば、障がい者向けの就活エージェントや転職サイトを活用することで、自分に合った企業を見つけやすくなります。
さらに、職業訓練やキャリアアップの支援を受けることで、より多くの選択肢を得ることができるでしょう。
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる
40代以降は「スキル・経験」がないと厳しくなる40代以上の求職者にとって、就職はやや厳しくなる傾向があります。
企業側は即戦力を求めることが多く、「これまでの職務経験やスキルを活かせるかどうか」が重要なポイントになります。
そのため、スキルや職歴が不足していると、応募できる求人が限られてしまうことがあります。
特に、これまでのキャリアが事務職や製造業などの特定分野に偏っている場合、新しい業種に転職するハードルが高くなることがあります。
40代以上の求職者は、これまでの経験を活かせる職種を中心に探しながら、必要に応じてスキルアップを図ることが大切です。
また、障がい者向けの求人でも、40代以上の採用に積極的な企業は限られているため、ハローワークや専門の就職支援機関を活用して幅広く情報を収集することが重要です。
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い
50代以上は「短時間勤務」「特定業務」などに限られることが多い50代以上になると、障がい者雇用枠での求人はさらに限られてきます。
企業側としては「体力的な問題」「継続勤務の難しさ」などを考慮し、フルタイム勤務ではなく、短時間勤務や特定業務に絞った採用を行うことが多くなります。
例えば、事務補助やデータ入力、清掃業務など、負担の少ない業務が中心となる傾向があります。
また、企業側も「シニア向けの障がい者雇用」を積極的に進めるケースが増えていますが、求人数自体は若年層向けと比べるとかなり少なくなります。
そのため、50代以上の求職者は、就職活動の選択肢を広げるために、パート・アルバイトや契約社員の求人も視野に入れるとよいでしょう。
また、就労支援機関を活用することで、自分に合った働き方を見つける手助けを受けることができます。
dodaチャレンジなどの就活エージェントのサービスに年齢制限はある?
障がい者向けの就活エージェントには、基本的に年齢制限はありません。
しかし、実際には20〜40代の求職者をメインターゲットとするケースが多く、50代以上の求職者の求人紹介は限られることがあります
年齢制限はないが 実質的には「50代前半まで」がメインターゲット層
dodaチャレンジなどの障がい者向け転職エージェントでは、公式には年齢制限を設けていません。
しかし、実際の求人市場を見ると、50代以上の求職者向けの案件は少なく、40代までの方が多くの選択肢を持てる傾向にあります。
そのため、50代以上の方が就職活動を行う場合は、転職エージェントだけに頼らず、ハローワークや地域の就労支援機関も併用しながら進めるのが効果的です。
特に、シニア向けの障がい者雇用枠や、短時間勤務の求人を探す際には、公的な機関の情報を活用するとよいでしょう。
ハローワーク障がい者窓口や障がい者職業センター(独立行政法人)も併用するとよい
50代以上の求職者が仕事を探す場合、dodaチャレンジなどの民間の転職エージェントに加えて、公的な支援機関を活用することが重要です。
ハローワークの障がい者窓口では、障がいのある求職者向けに、個別相談や求人紹介、履歴書添削などのサポートを提供しています。
また、独立行政法人である障がい者職業センターでは、就職活動のサポートに加え、職業訓練や実習の機会も提供しており、スキルアップを目指す方にとって有益な情報を得ることができます。
50代以上の方が就職を成功させるためには、転職エージェントだけに頼らず、複数の支援機関を活用しながら、幅広い選択肢を検討することが大切です。
シニア向けの求人や、障がい者雇用枠の中でも経験を活かせる仕事を探すことで、より安定した就職につながるでしょう。
dodaチャレンジで断られたときの対処法について|よくある質問と回答
dodaチャレンジを利用して転職活動を進める中で、「求人を紹介してもらえなかった」「面談後に連絡が来ない」といった状況に直面することがあります。
これは、スキルや経験、希望条件などによって変わるため、一概に「紹介してもらえない=就職が難しい」というわけではありません。
しかし、適切な対策を取ることで、チャンスを広げることは可能です。
ここでは、dodaチャレンジで断られた場合の具体的な対処法について、よくある質問をもとに解説していきます。
dodaチャレンジの口コミや評判について教えてください
dodaチャレンジの口コミには、さまざまな意見があります。
良い口コミでは、「キャリアアドバイザーが親身に相談に乗ってくれる」「障がい者雇用に特化した求人が多い」「書類添削や面接対策が丁寧」などの声があります。
一方で、「希望に合う求人が見つからなかった」「スキル不足を理由に求人を紹介してもらえなかった」という声も見られます。
転職活動では、自分のスキルや希望条件と市場のニーズを照らし合わせることが大切です。
もしdodaチャレンジで希望する求人が見つからない場合は、他の障がい者向け転職エージェントを併用するのも有効な手段です。
関連ページ:dodaチャレンジの口コミは?障害者雇用の特徴・メリット・デメリット
dodaチャレンジの求人で断られてしまったらどうすれば良いですか?
dodaチャレンジで求人を紹介してもらえなかった場合、まず「なぜ紹介されなかったのか」を確認することが大切です。
主な理由として以下のようなものがあります。
– スキル不足(PCスキルや専門知識が求められる仕事に応募した場合)
– 希望条件が厳しすぎる(在宅勤務限定、短時間勤務、高年収など)
– 障がいの特性と業務のマッチングが難しい(配慮が必要な項目が多い場合など)このような場合は、ハローワークの職業訓練や就労移行支援を利用してスキルアップを図るのも一つの方法です。
また、希望条件を少し見直すことで、紹介可能な求人が増えることもあります。
さらに、dodaチャレンジ以外の障がい者向け転職サービス(atGP、エージェント・サーナなど)を併用することで、より多くの求人に出会える可能性があります。
関連ページ:dodaチャレンジで断られた!?断られた理由と対処法/難しいと感じた体験談
dodaチャレンジで面談後に連絡なしの理由について教えてください
dodaチャレンジの面談を受けた後、すぐに連絡が来るとは限りません。
通常、1週間以内には何らかの連絡がありますが、状況によってはそれ以上かかることもあります。
面談後に連絡がない理由として、以下のようなものが考えられます。
– 現在の希望条件に合う求人がないため、求人が出るまで待機状態になっている
– 求人検索中で、適切な案件を探している段階である
– メールが迷惑フォルダに入っている、または誤って削除されてしまった
– 担当アドバイザーの業務状況によって、対応が遅れている1週間以上経っても連絡がない場合は、メールや電話で担当者に問い合わせてみるとよいでしょう。
状況を確認することで、次のステップが見えてくることがあります。
関連ページ:dodaチャレンジから連絡なしの理由と対処法/面談・求人・内定それぞれのケースと連絡なしの理由
dodaチャレンジの面談の流れや聞かれることなどについて教えてください
dodaチャレンジの面談では、キャリアアドバイザーが求職者の状況を詳しくヒアリングし、最適な求人を提案してくれます。
面談の流れは以下のようになります。
1. 自己紹介とこれまでの職歴・経験の確認
2. 障がいの特性や配慮事項についてのヒアリング
3. 希望する職種・業界・勤務地・働き方についての確認
4. 持っているスキルや資格、得意なことの整理
5. 求人の紹介(※適合する求人がある場合)特に、障がいの内容や職場で必要な配慮事項については、しっかりと伝えることが重要です。
アドバイザーが企業に適切に伝えてくれるため、安心して働ける環境を見つけやすくなります。
面談前には、希望する職種や配慮事項を整理し、履歴書や職務経歴書を準備しておくとスムーズに進めることができます。
関連ページ:dodaチャレンジの面談から内定までの流れは?面談までの準備や注意点・対策について
dodaチャレンジとはどのようなサービスですか?特徴について詳しく教えてください
dodaチャレンジは、障がいを持つ方々の就職支援を行うサービスです。
主に障がい者向けの求人情報を提供するだけでなく、個別のキャリアカウンセリングや面接対策、就職後のフォローアップも実施しています。
利用者の障がいに配慮した職場を紹介し、マッチングを図ることに重点を置いています。
また、オンラインでのサポートが充実しており、自宅にいながらでもサービスを受けることができます。
利用者一人ひとりのニーズに合わせた、個別対応を行うことが特徴です。
障がい者手帳を持っていないのですが、dodaチャレンジのサービスは利用できますか?
dodaチャレンジのサービスは、障がい者手帳を持っていない方でも利用することができます。
手帳を持っていない方でも、身体的または精神的な障がいがあると認識される場合には、サービスを利用することが可能です。
手帳を所持していない方でも、個別のカウンセリングや就職サポートが提供されるため、障がいを持つ方々が自分に合った仕事を見つける手助けをしてくれます。
利用者に寄り添った支援を行うため、手帳の有無に関わらず安心して利用できます。
dodaチャレンジに登録できない障害はありますか?
dodaチャレンジは、多くの障がいに対応しており、幅広い方々をサポートしていますが、一部、就労に大きな制限がある障がいについては、登録が難しい場合があります。
例えば、極端に重度の障がいがある場合や、職場での勤務が困難な場合などが該当することがあります。
しかし、サービスの利用が難しい場合でも、他の福祉的支援がある場合があるため、まずは相談することが大切です。
障がいに関わらず、可能な限り多くの方にサポートを提供しています。
dodaチャレンジの退会(登録解除)方法について教えてください
dodaチャレンジの退会方法は、公式サイトを通じて簡単に行うことができます。
退会を希望する場合、マイページから退会手続きができ、必要事項を入力することで処理が完了します。
また、サポートセンターに連絡をすることで、担当者が手続きを案内してくれます。
万が一、退会後に再度サービスを利用したい場合も、再登録が可能です。
退会手続きはシンプルで、特別な理由がなくても簡単に解除することができます。
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングはどこで受けられますか?
dodaチャレンジのキャリアカウンセリングは、オンラインでの相談と、全国の相談窓口で受けることができます。
オンラインでのカウンセリングは、自宅や職場などからアクセスできるため、便利で時間を気にせず利用できます。
また、直接相談したい方のために、全国の拠点でも対面でのカウンセリングを受けることができます。
どちらの方法でも、専門のカウンセラーが対応し、就職活動に必要なアドバイスを提供してくれます。
dodaチャレンジの登録には年齢制限がありますか?
dodaチャレンジには年齢制限は特に設けられていません。
障がいを持っている方であれば、年齢に関わらずサービスを利用することができます。
若年層からシニア層まで、さまざまな年齢層の利用者がいるため、個々のライフステージに応じた就職支援が行われています。
年齢を気にせず、自分のペースでサポートを受けることができ、どの年代でも適切なアドバイスを得ることができます。
離職中ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
離職中の方でも、dodaチャレンジのサービスを利用することができます。
離職後に新しい職を探すためのサポートを提供しており、キャリアカウンセリングや求人の紹介、面接対策を受けることができます。
特に、就職活動を再開する際には、自己分析やスキルアップのための支援が重要です。
離職後の方々にとっても、自分に適した職場を見つける手助けをしてくれるので、安心して利用することができます。
学生ですがdodaチャレンジのサービスを利用できますか?
dodaチャレンジは、学生でも利用することができます。
特に、卒業前に就職活動を始めている学生に対して、企業の情報提供や面接対策を行っています。
障がいを持つ学生が、就職活動をスムーズに進めるために必要なサポートが充実しており、企業とのマッチングを通じて、自分に合った職場を見つけることができます。
学生のうちから障がいに配慮した仕事を探すことができ、就職活動の成功をサポートしてくれるサービスです。
参照:よくある質問(dodaチャレンジ)
dodaチャレンジは断られない?その他の障がい者就職サービスとの比較一覧
dodaチャレンジは、障がい者雇用に特化した人材紹介サービスで、求職者が企業とのマッチングにおいて断られるリスクを減らせる点が特徴です。
キャリアアドバイザーが求職者のスキルや希望をヒアリングし、適性に合った求人を紹介するため、選考がスムーズに進むケースが多く見られます。
一般的な求人サイトでは、自分で求人を検索して応募する必要がありますが、dodaチャレンジではアドバイザーが間に入り、企業とのコミュニケーションをサポートしてくれるため、より適切な選考対策が可能です。
他の障がい者向け就職サービスと比較しても、dodaチャレンジは非公開求人を含む豊富な案件を保有しており、選考通過率が高いと評判です。
また、障がい者雇用に理解のある企業の求人が中心であるため、応募後に断られるリスクが低く、初めての転職活動でも安心して進められるメリットがあります。
キャリアアドバイザーの丁寧なサポートを受けながら、自分に合った企業を見つけたい方にとって、dodaチャレンジは有力な選択肢と言えるでしょう。
| 就職サービス名 | 求人数 | 対応地域 | 対応障害 |
| dodaチャレンジ | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| アットジーピー(atGP) | 1,500 | 全国 | 全ての障害 |
| マイナビパートナーズ紹介 | 350 | 全国 | 全ての障害 |
| LITALICOワークス | 4,400 | 全国 | 全ての障害 |
| 就労移行支援・ミラトレ | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| ランスタッドチャレンジ | 260 | 東京、神奈川、千葉、埼玉、大阪 | 全ての障害 |
| Neuro Dive | 非公開 | 全国 | 全ての障害 |
| Cocorport | 非公開 | 首都圏、関西、東海、福岡 | 全ての障害 |
dodaチャレンジで断られた!?断られた理由や対処法|難しいと感じた詳しい体験談まとめ
dodaチャレンジで断られる理由の一つは、求人企業が求めるスキルや経験に対して応募者の条件が一致しない場合です。
また、応募が集中するタイミングではポジションが早期に埋まってしまうこともあります。
さらに、障がい者雇用枠では、企業側が重視する職場適応能力やスキルセットが独自の基準に基づいていることが多く、その条件に合わなければ選考を進めるのが難しくなるケースがあります。
応募者側の書類の内容や面接での自己PRが不足していると、企業側が採用に踏み切れないことも一因となります。
対策としては、まずキャリアアドバイザーに相談し、自分の希望条件やスキルに合った求人を改めて紹介してもらうことです。
履歴書や職務経歴書の内容を企業ごとに調整し、アピールポイントをしっかり記載することで、選考通過の確率を上げられます。
さらに、応募する前に企業の業界や求められるスキルをリサーチし、面接に備えることも重要です。
dodaチャレンジでは、アドバイザーの意見を参考にすることで次の応募に向けた改善点を見つけ、断られる確率を減らす工夫ができます。